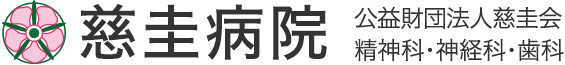キャリアアップ支援体制
学ぶ意欲を育み、スペシャリストとしてさらに新たな一歩を踏み出す。先輩たちのさりげないあたたかさが私たちを成長させてくれました。
「人生を載せて歩みたい。そして、なりたい自分になっていく」。個人のキャリアアップの支援体制、ここには整っています。


精神科認定看護師(退院調整領域)
看護副師長
慢性期病棟に勤務していた頃、「果たして自分に何が出来るのか、この人は、なぜ退院できないのか。」「病院という小さな世界の中でこの人は幸せなのか。」そんな思いを抱えていました。そんなとき、退院支援の研修に参加、実際に多職種で支援する方法や私たち看護師が地域に出て行く大切さを知り、病院の支援体制を最大限に活用して精神科認定看護師の資格を取得しました。
現在、私は訪問看護室に所属しACTチームの一員として精神疾患を抱えながら地域で生活されているかたの支援を担当しています。私が支援をするうえで大切にしていることは、患者さまの「思い」です。患者さまの心にその「思い」が生まれるように、まずは気持ちをしっかり聴くことが大切だと、経験を重ねるうちに感じるようになりました。また、患者さまの支援に必要なことはあきらめないこと。あきらめないことで患者さまの可能性や強みが発見できる。そしてスタッフの姿勢が変わることで患者さまやご家族も変化していくと感ています。「人は自分らしく生きることで笑顔になれる」という当院ACT(HARE ACT)の理念のもとで、患者さまが自立した生活ができるような活動を行っています。これからも一人でも多くのかたに、自分らしい生活が送れるよう支援していきたいと思っています。
看護副師長
慢性期病棟に勤務していた頃、「果たして自分に何が出来るのか、この人は、なぜ退院できないのか。」「病院という小さな世界の中でこの人は幸せなのか。」そんな思いを抱えていました。そんなとき、退院支援の研修に参加、実際に多職種で支援する方法や私たち看護師が地域に出て行く大切さを知り、病院の支援体制を最大限に活用して精神科認定看護師の資格を取得しました。
現在、私は訪問看護室に所属しACTチームの一員として精神疾患を抱えながら地域で生活されているかたの支援を担当しています。私が支援をするうえで大切にしていることは、患者さまの「思い」です。患者さまの心にその「思い」が生まれるように、まずは気持ちをしっかり聴くことが大切だと、経験を重ねるうちに感じるようになりました。また、患者さまの支援に必要なことはあきらめないこと。あきらめないことで患者さまの可能性や強みが発見できる。そしてスタッフの姿勢が変わることで患者さまやご家族も変化していくと感ています。「人は自分らしく生きることで笑顔になれる」という当院ACT(HARE ACT)の理念のもとで、患者さまが自立した生活ができるような活動を行っています。これからも一人でも多くのかたに、自分らしい生活が送れるよう支援していきたいと思っています。

精神看護専門看護師
看護部長
看護師としてのスタートは一般科でした。その病棟では、患者さまとの関係の中で治療がうまくいかないケースについて、精神科医を交えたリエゾンカンファレンスを行っており、カンファレンスでの精神科医のアドバイスでケアを考え直すきっかけになっていました。精神科に興味を持ち精神科に異動しましたが、精神科の中でケアがうまくいかないケースがいくつもありました。カンファレンスでアセスメントや自分たちのケアを話し合い、解決策を探しましたが、看護は何を行うのか、何ができるのか、なかなか答えは見つかりませんでした。精神科看護についてきちんと学びたいと思い、大学院に進学しました。大学院で学ぶことで、ばらばらだったものがつなぎ合わされ、精神科での看護が見えるようになりました。精神科看護は、「こうやったらうまくいく」といった正解はありません。患者さまの思いを大切にしながら、患者さまの言動のひとつひとつの意味を考え、何が起きているのか理解し、ケアにつなげていきます。患者さま一人ひとりにじっくりと向き合い、その人が抱える困難について、一緒に考えながら進んでいくことが看護師の役割です。また、多職種の協働で、それぞれの専門性を生かし患者さまに関わることで、その人らしい生活を支えることができます。専門看護師として、患者さまに最も良いケアが提供できるように、専門的知識と技術に基づいて判断し、患者さまの状態のアセスメントや、ケアで現在行われていること、ケアの方策などを言葉で伝えることで、スタッフの方たちとケアを考えています。スタッフの皆様が、看護の面白さを感じ、さらにより良いケアを目指していただけるとうれしいです。
看護部長
看護師としてのスタートは一般科でした。その病棟では、患者さまとの関係の中で治療がうまくいかないケースについて、精神科医を交えたリエゾンカンファレンスを行っており、カンファレンスでの精神科医のアドバイスでケアを考え直すきっかけになっていました。精神科に興味を持ち精神科に異動しましたが、精神科の中でケアがうまくいかないケースがいくつもありました。カンファレンスでアセスメントや自分たちのケアを話し合い、解決策を探しましたが、看護は何を行うのか、何ができるのか、なかなか答えは見つかりませんでした。精神科看護についてきちんと学びたいと思い、大学院に進学しました。大学院で学ぶことで、ばらばらだったものがつなぎ合わされ、精神科での看護が見えるようになりました。精神科看護は、「こうやったらうまくいく」といった正解はありません。患者さまの思いを大切にしながら、患者さまの言動のひとつひとつの意味を考え、何が起きているのか理解し、ケアにつなげていきます。患者さま一人ひとりにじっくりと向き合い、その人が抱える困難について、一緒に考えながら進んでいくことが看護師の役割です。また、多職種の協働で、それぞれの専門性を生かし患者さまに関わることで、その人らしい生活を支えることができます。専門看護師として、患者さまに最も良いケアが提供できるように、専門的知識と技術に基づいて判断し、患者さまの状態のアセスメントや、ケアで現在行われていること、ケアの方策などを言葉で伝えることで、スタッフの方たちとケアを考えています。スタッフの皆様が、看護の面白さを感じ、さらにより良いケアを目指していただけるとうれしいです。